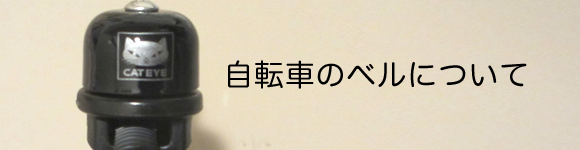
結論から書けば、自転車のベルは法律で装備が義務付けられています。
自転車のベルと言えば、歩行者に「自転車が通りますよ。どいてください。」というような意味で使用する人も多いと思いますが、自転車のベルは無闇矢鱈に鳴らして良いものではなく、実はごく限られた場所やシチュエーションでしか鳴らすことができません。
実際のところで、自転車のベルを鳴らせるようなシチュエーションが日常では無いに等しいので、自転車のベルの装着義務について疑問を感じる人も多いようです。
僕自身も自転車のベルについてよく理解していない部分もあったので、自転車のベルは「いつ鳴ららして良いのか?」そして、「そもそも自転車のベルは必要なのか?」などについて調べてみました。
道路交通法と自転車のベル(警音器)

自転車にはベルの装備が必須
クロスバイクやロードバイクなどのスポーツバイクはもちろん、一般的なママチャリまで含めて、公道を走る全ての自転車にはベル(警報機)の装備が義務づけられています。
一般的なママチャリには購入時からベルが装備されているので、壊れていない限りはベルは装備されているものと思われます。
サイクルショップなどでも、法律に違反するような自転車は販売できないので、レースでしか使用しないなどの例外を除けば、購入時にはベルが装備された状態で販売されていることがほとんどかと思います。
しかしながら、冒頭にも書いたように、自転車のベルを鳴らせるシチュエーションがほとんど無いことから、自転車のベルは不要と思い、ベルを外してしまう人も中には居るようです。
僕自身も、自転車にはベルの装備が必須ということを知りませんでした。
しかし、よくよく考えれば、自転車も自動車やバイクなどと同じ車両ですから「警笛鳴らせ」の標識がある場所では警笛を鳴らす必要があるわけです。
言い方を変えると、「警笛鳴らせ」の標識がある場所では、ベルを鳴らさなくてはいけないので、ベルの装備が必要になります。
なので、警笛を鳴らせない時点で、道路交通法違反となるので、ベルの装備をしていないと駄目なわけです。
道路交通法と警音器(ベル)の装備について
自転車(軽車両)のベル(警音器)の装備や鳴らす必要のある場所に関する法律をまとめてみました。
道路交通法第54条(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
[5万円以下の罰金等]
自転車は軽車両ではありますが、「自転車以外の軽車両を除く。」とあるので、自転車は除外されておらず、車両として扱われるため、「警笛鳴らせ」の標識がある場所では、ベルを鳴らさなくてはいけないのです。
道路運送車両の保安基準
第四章 軽車両の保安基準
(警音器)
第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
道路運送車両法
道路運送車両法でも、軽車両には警音器の装備が義務付けられています。
(軽車両の構造及び装置)
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器
東京都自転車安全利用指針
第4節 自転車の安全利用に必要となる一般的な知識
第3 自転車の通行場所等
6 歩道の通行に関する条件、通行場所及び通行方法
(3) 通行方法
イ 警音器は危険を防止するためやむを得ない場合に鳴らすものです。歩行者に自分の存在を気付かせたり、進路を譲らせたりする目的で警音器を鳴らしてはなりません。(東京都自転車安全利用指針より引用)
第4節 自転車の安全利用に必要となる一般的な知識
第8 安全な自転車の利用、他者への配慮等 ····
1 東京都自転車点検整備指針を踏まえて点検整備した自転車を利用するよう努めなければなりません。特に、警音器、ブレーキ、前照灯及び反射器材又は尾灯灯が壊れた自転車を利用することは禁止されています。(前照灯、反射器材又は尾灯については、夜間等に限ります。)(東京都自転車安全利用指針より引用)
第5節 自転車の安全利用に必要となる発展的な知識····
第5 警音器 ·
1 みだりに警音器を鳴らしてはなりません。
2 右の道路標識によって指定された場所や区間における左右の見通しの利かない交差点や道路の曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければなりません。(東京都自転車安全利用指針より引用)
右の標識ってのは
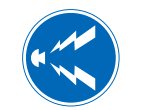
警笛鳴らせの標識です。(国土交通省:道路標識一覧(PDF 760KB)より引用)
自転車の警音器(ベル)は基本的に鳴らしてはけない
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
[5万円以下の罰金等]
自転車には警音機(ベル)の装備が義務づけられてはいるものの、どこでも鳴らして良いというわけではありません。
昔のテレビのドラマなどでも「チリリン」と自転車に乗った主人公がベルを鳴らしながら、街なかを走るシーンなどがあったりしますが、法律的にはやってはいけない行為となります。
実際の日常でも走行中に歩行者に対して「自転車が通るから寄ってちょうだい」的な意味でベルを鳴らしたりしている人もよく見かけますがそれも違反行為です。
たとえ目の前で歩行者に道を塞がれていても、自転車はベルを鳴らしてはいけません。
警音機(ベル)の使用は基本的には「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所に限られています。
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所ではベルを鳴らす必要があるので、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所でベルを鳴らすためにベルを装備しているわけです。
しかし、一般的に「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所は街なかではなく、山道などで見通しが悪い場所でしかみかけないような標識なので、よっぽどのことがない限りは、自転車に乗っていて「警笛鳴らせ」の道路標識に出会うことはまずありません。
なので、日常生活において、自転車のベルを鳴らさなくてはいけない場所はほとんど無いのです。
逆に言えば、日常生活において、ほとんどの場所ではベルを鳴らしてはいけないのです。
危険を防止する時ってどんな時?
自転車のベルは日常では鳴らしてはいけない場所がほとんどですが、「危険を防止するのにやむおえない時」には例外的にベルを鳴らして良いことになっています。
問題は、法律用語というのは日頃使わない言葉も多数出てくるので、解釈が難しいことも多く、勘違いしてしまう場合もあります。
SNSで警音機(ベル)について言及されている方のコメントを確認してみても、様々な意見が見受けられます。
例えば、目の前に視界の悪い脇道があり、もしかしたら自転車や歩行者が飛び出してくるかもしれないというシチュエーションの場合、相手に自分の存在を知らせるために(予想される危険を回避するために)警音機(ベル)を鳴らすのは良い(むしろ鳴らさなきゃしけない)と考える人もいたりします。
しかし、実際は、警音機(ベル)を鳴らしてはいけない場合がほとんどです。
なぜならば、単に見通しの悪い交差点などでは、警音機(ベル)を鳴らさなくても、一時停止するなどして安全を確認すれば危険は回避できるからです。
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
警音機(ベル)をを鳴らしても良いと判断する人は、おそらく「左右の見通しの利かない交差点や道路の曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければなりません。」という部分を踏まえての意見だと思います。
しかし、その前にある「道路標識によって指定された場所や区間における」という言葉を見落としてしまっているものだと思われます。
「危険を防止するのにやむおえない時」については、解釈が難しい問題でもあるので、より正しく理解するために下記の記事で深掘りしていますので、参考にしてください。
僕のクロスバイクに使用しているベルの紹介

僕のクロスバイクには、CATEYE製の小さなベルを装備しています。
CATEYEのベルは、10円玉くらいの大きさの小さなベルで、装備していてもほとんど存在感がありません。
あまり使用する機会がないものですから、軽くて目立たない小さなベルが良いなと思い選択しました。

ベルの正面には、CATEYEのロゴである猫の顔。
可愛いですね。

タイラップを外せます。
このタイラップはキャットアイ製のサイクルコンピューターなどとも共用できます。

奥行きはこんな感じ。

キャットアイのサイクルコンピュータを固定してあるタイラップと共用してベルを取付けています。

ステムの真下に付けても良いと思いますが、正面や真横から見た際に、ベルのシルエットが目立ってしまうので、ハンドルとステムの陰にひっそりと装備しています。
その後、knogというメーカーから発売に鳴った、Oiと呼ばれるベルに交換しました。
こちらはハンドルに取り付けても目立たないようなデザインになっていて、多くのサイクリストからの評価も高いベルです。
knog Oiのレビューはこちら
【日本正規品】 KNOG(ノグ)自転車 ベル Oi CLASSIC BELL リング型(内径:23.8-31.8mm) LARGE ブラック |2年...







